住民訴訟ってなに?
住民訴訟とは、地方自治体のお金の使い方や契約に“おかしい点”があるときに、住民が「それはダメでしょ!」と裁判でチェックを求められる仕組みのこと。
本来、税金の使い方を一番近くで見守るのは自治体の職員や議会なんだけど、もし彼らが見逃してしまったら、住民が“代理のチェック役”として声をあげられるんだよね。
相続に例えると?
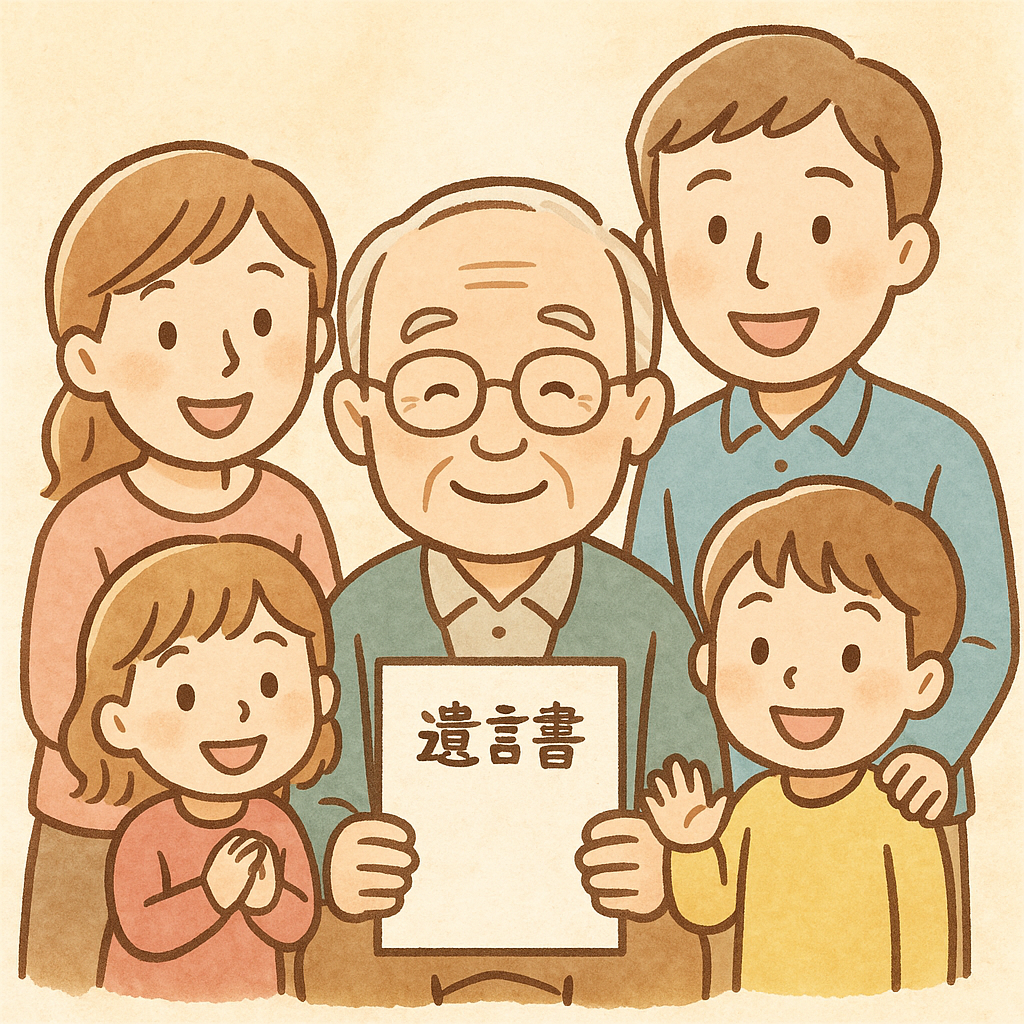
例えば、亡くなったおじいちゃんの遺産を分ける場面を考えてみよう。
相続人(家族)がきちんと遺産分割をすれば問題ないけど、もしある相続人が勝手に遺産を使い込んでしまったら…?😱
このとき、他の相続人が「ちゃんと皆で公平に分けて!」と異議を申し立てるよね。
これがまさに住民訴訟に似ているの。
つまり「みんなの財産(=遺産や税金)」を守るために、身近な立場の人(=相続人や住民)がチェックする、という構図なんだ。
住民監査請求との関係
ただし住民訴訟をいきなり起こすことはできないの。
まずは「住民監査請求」といって、自治体に「お金の使い方を調べて!」とお願いする必要があるんだよ。
相続でいうなら、「まずは遺産の使い込みについて専門家(遺産分割協議の立会人や弁護士)に確認してもらう」イメージ。
それでも解決しなければ、裁判という強い手段=住民訴訟につながっていくんだよね。
まとめ:相続人のチェック役=住民の役割
住民訴訟は、相続で相続人が「不正をただす役割」を果たすのと同じで、住民が「税金の番人」になる制度。
自分のお金だけじゃなくて、みんなのお金(=税金)を守るために、住民が最後の砦になるんだよ。

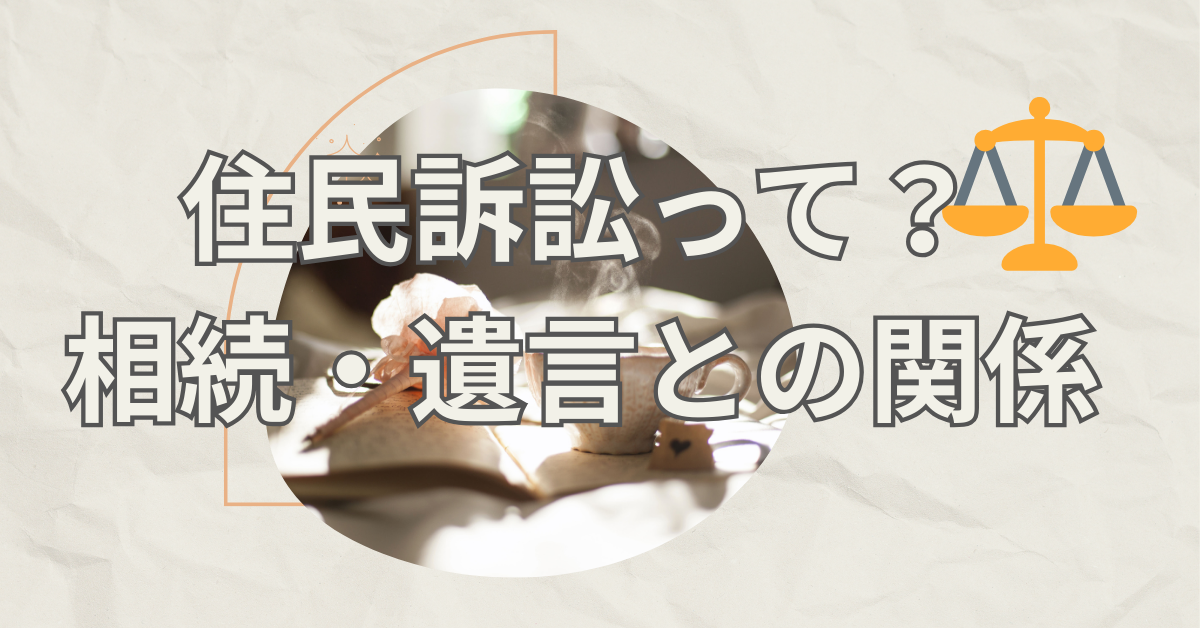
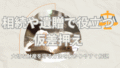
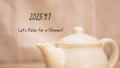
コメント