仮の義務付けと仮の差止め 〜行政事件訴訟法37条の5をやさしく解説〜
こんにちは🌸
行政書士の勉強をしていると、「仮の義務付け」・「仮の差止め」について「仮って何?」・「仮じゃなくなるのはいつ?」と、疑問に思うことありませんか?🥹
今日は行政事件訴訟法37条の5を、やさしく、遺産の場合のイメージを交えながら解説していきますね✨
そもそも「仮の義務付け」と「仮の差止め」ってなに?🤔
かんたんに言うと…
仮の義務付け 👉 行政に「とりあえずやってもらう」制度
仮の差止め 👉 行政に「とりあえずやめてもらう」制度
まだ裁判の結論が出ていない段階でも、「今すぐ動いてもらわないと困るよ〜!」ってときに使える救済制度なんです🌱
遺産に例えて考えると、わかりやすいよ
✅ 仮の義務付けのイメージ
相続の手続きで「遺産分割協議書を添えて申請したのに、市町村が証明書を交付してくれない…😱」
👉 そのままだと登記が遅れて大きな不利益!
だから「とりあえず交付して!」とお願いできるのが仮の義務付け。
✅ 仮の差止めのイメージ
亡くなった人の土地について、行政が「公共事業だから収用手続きを進めます!」と動こうとしている場合。
👉 裁判を待っていたら工事がどんどん進んで遺産が失われちゃう💦
だから「とりあえずストップして!」とお願いできるのが仮の差止め。
📍ポイントまとめ
- どちらも「本案判決が確定するまでの暫定的なお願い」
- 本案判決が出れば効力は消える(=“仮”が外れる)
- 急を要する場面で、不利益を避けるために使われる制度
要件は3ステップで理解!
1.重大な損害を避けるため、必要!
🤔💭(相続財産を失うと取り返しがつかない…)
2.回復困難な損害の可能性
🤔💭(お金で補えない損害が生じるかどうか)
3.公共の福祉との比較衡量
🤔💭(相続人の利益と公共事業、どちらを優先するか⚖️)
上記の3つが全て揃わないとダメだよ。
試験に出やすい比較ポイント📘
義務付け
=行政に「何かさせる」👉 GO!
差止め
=行政に「やめさせる」👉 STOP!
この違いが頭に入っていれば、混乱することもないよ。
まとめ🌸
相続や遺贈の場面でも、「裁判の結果を待っていたら遅すぎる!」って時に、
この救済制度があるんだなってイメージできると安心だね☺️💐

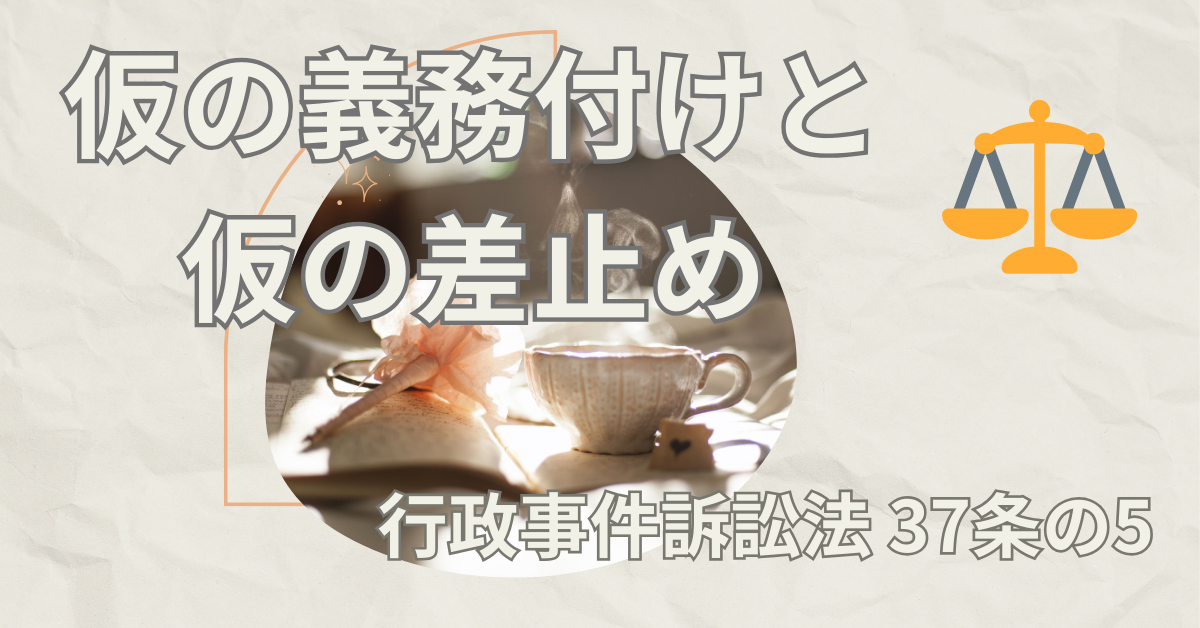
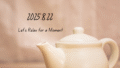
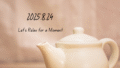
コメント